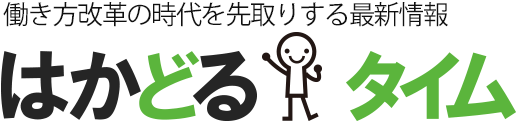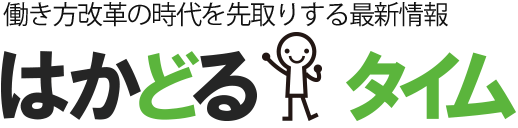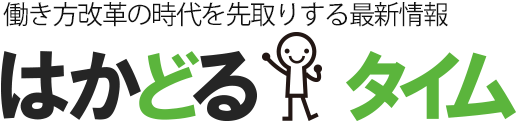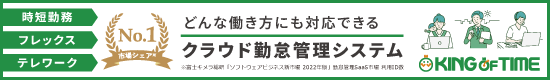労働の時間制と変形期間!またそれに関わる導入要件
2015.04.30
企業によって繁忙期、閑散期というものは必ずありそれに合わせた変形労働時間を採用している企業も多いです。またこの制度は労働側にとってもワークライフバランスを取る意味でメリットのある制度といえるでしょう。

変形労働時は労基法事ある法定労働時間の週40時間を平均として捉え変形期間に振り分けるものです。変形期間(対象期間)が1年単位の変形労働時間制は「1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと」とあります。
1か月単位の変形労働時間制では「1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないこと」との基本要件があります。
これらの変形労働時間制は使用者が一方的に決められるものではなく労使協定を締結している必要があります。この労使協定では労働者の範囲の明記、対象期間・起算日の明記が必要です。またシフト表や会社カレンダーなどで対象期間の労働日ごとの労働時間を事前に明記しておく必要がありますのでご注意ください。
また、この協定の有効期間については1か月単位の場合3年程度、1年単位の場合1年程度というガイドラインがあります。労使協定を結ぶことで就業規則の書き換えなども必要となりますのでご留意ください。
フレックスタイム制は、1日の労働時間帯をコアタイム(必ず勤務する時間帯)とフレキシブルタイム(出社時間・退社時間が労働者の裁量に任されている時間)に分けて運用する制度です。
例えばフレキシブルタイムを午前7時から午後7時まで、コアタイムを午前10時から午後3時と設定した場合、午前8時に出勤して午後5時に退勤、午前10時に出勤して午後7時に退勤といった働き方が選べることになります。
会社側にしてみれば部署によって違う忙しい時間帯の対策に有効で時間外労働抑制効果が期待できます。労働側にとっては子育て中や趣味の時間など自分のライフスタイルに勤務時間を合わせられるメリットがあります。
このフレックスタイム導入に当たっても労使協定を結び基本的枠組みを労使間で取り決めておく必要があります。基本的枠組みは対象労働者・清算期間とその起算日・清算期間の総労働時間・標準となる1日の労働時間・コアタイム、フレキシブルタイムの開始、終了時間などが必要です。
変形労働時間制はいわば固定的に運用されていた所定労働時間を忙しい時期・時間に振り分ける制度です。そのため所定時間内の労働は残業とはなりません。所定時間を超えての勤務が時間外労働となりますのでこの点をご留意ください。
変形労働時間は所定労働時間をフレキシブルに運用する制度です。実施には労使協定や就業規則の書き換えなども必要となります。
おすすめの記事

掃除や家事は運動になる!家事の運動量や消費カロリーはどのくらい?
2024.05.15 - コラム

食いしばりや歯ぎしりは歯を痛める原因に!改善の方法は?
2024.05.10 - コラム

やむを得ない事情で夜遅くの食事に 遅い時間に食べてもいい食品は?
2024.05.03 - コラム