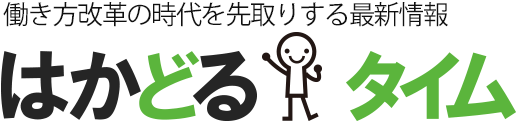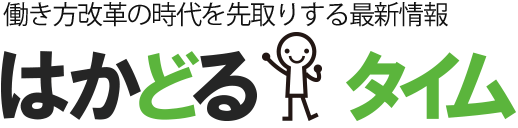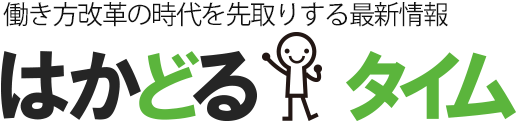企画業務型裁量労働制とは?導入法と注意点
2018.09.30
近年、働き方改革による生産性向上の観点からも、より柔軟な労働形態・就業形態の導入に関心が高まっています。社会構造の変化や個々人のライフスタイルの尊重を踏まえながら、さらなる経済活動の発展を図っていくため、仕組みから見直す工夫は不可欠ですが、そのためには労働者側にも雇用者側にも、しっかりとした予備知識が必要です。
みなし労働時間制という言葉や裁量労働制といった労働のかたちを耳にしたことがある方は多いと思われますが、その詳細規定内容や正しい導入・運用方法などとなると、十分に理解している自信のある方は少数でしょう。
さらにこの裁量労働制には、よく知られる対象19職種を特定した専門業務型のほかに、企画業務型と呼ばれるタイプもあります。そこで今回は昨今注目を集めている、この「企画業務型裁量労働制」について、特徴や導入注意点など、基礎から解説していきます。

労働基準法における労働時間は、実労働時間で算定することを基本原則としていますが、中には、1日の大半を社外労働とするために正確な労働時間算定が困難な業務や、業務の遂行方法などを労働者個人の裁量に委ねる方が適切で使用者の具体的な指揮監督が及ばないような業務もあります。
こうしたものに合理的な対処をとれるよう、実際の労働時間にかかわらず、成果などからその日をあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす、みなし労働時間制という制度が用意されています。
このうち、外回りの営業職などを中心に、事業場外で働くことがメインなケースで採用するのが「事業場外労働」で、それ以外が「裁量労働制」、さらに裁量労働制のうち、高度な専門性・裁量性をもって業務遂行の手段や時間配分を自ら決定しながら働く、指定19職種が対象となるのが「専門業務型裁量労働制」です。
そして残るひとつが、今回取り上げる「企画業務型裁量労働制」と呼ばれるもので、2000年の改正法施行で新設された、比較的新しいタイプの制度となっています。主に、企業の統括部門を担うホワイトカラー層で適用することが想定されていますが、最も導入要件など内容が複雑となっていますから、活用する場合には注意も必要です。
企画業務型裁量労働制が適用できるのは、企業の経営や事業運営に直接大きな影響を与えるような、重要度の高い企画立案・調査・分析業務に携わる労働者で、その業務を進められるだけの十分な知識や経験があり、自身の考えで働き方を決定できるケース、その労働者自身もこうした業務従事の仕方に同意しているケースです。
原則として3~5年程度の職務経験があることが前提になっており、あくまで会社の舵取りを担う主体となっている労働者であることがポイントです。広義の調査分析業務でも、上司から指示を受け、その監督の下、事務作業として処理を行い報告するといった労働者には適用できません。社をあげて行う新規事業の開拓などでも、企画課部門全体が対象となるわけではなく、個々の労働者で判断されるものとなっています。
本社・本店でなければならないといった、事業場および勤務地についての限定規定はありませんが、事業運営に大きな影響を与える決定がなされる事業場、本社・本店の指示を受けず独自に該当する事業場の運営を決定づけていくような事業契約を結んでいる支社・支店などであることが導入指針として示されています。
企画業務型裁量労働制を導入する場合には、まず就業規則にその旨を書き込んでおく必要があります。そして対象となる事業場にその業務が存在することを明確にし、所轄の労働基準監督署に使用者が届出を行うことが求められます。
その上で、労使委員会を組織し5分の4以上の賛成決議を得なければなりません。労使委員会は、その半数について、対象となる事業場の労働者の過半数で組織される労働組合か、それがない場合は過半数を代表する人に任期を定めて指名されている者でなければならないとされています。委員会の議事については、議事録を作成の上保存するとともに、その内容が労働者全体へ周知されるようにする必要もあります。
こうした労使委員会で、対象業務や対象労働者の範囲、1日あたりのみなし労働時間数といった基本項目のほか、対象労働者で過重労働による健康被害などが生じないよう、健康・福祉面の具体的措置をどうとるか、対象者から苦情が出た場合にはどうするか、同意しない労働者に不利益な扱いをしない旨の取り決めなどを話し合い、出席している委員全員の5分の4以上で決議することが、導入の条件となります。
内部で決議するだけでなく、その旨を労働基準監督署に届け出ることも必須で、届出がなされなければ制度の正式導入はできず、効力も発生しません。
こうした要件が満たされた上で、対象となる労働者本人の同意が最終的に必要です。運用開始となった後も、決議が行われた日から6カ月以内に、所定様式による所轄労働基準監督署への定例報告が求められ、健康・福祉の確保措置などが適切に運用されているか、チェックされる仕組みともなっています。
決議の有効期間は3年以内が望ましいとされ、さらに継続する場合は、再び労使委員会の決議、本人の同意確認が必要になります。
企画業務型裁量労働制が適用されると、ある特定の日の実労働時間が10時間であっても、法定労働時間の8時間をみなし労働時間としていれば、8時間と扱われ、逆に2時間しか働いていなくても、同じ8時間と取り扱われることとなります。
これにより、労働者はより高い自由度のある環境のもと、創造性を発揮した働きなどがフレキシブルに行いやすくなり、企業側・使用者側は、より成果を重視した効率の良い業務遂行実現、さらなる生産性向上へと、全体を導きやすくなると考えられています。
しかし制度が乱用されると、残業代の不払いを目的とした適用や、労働の長時間化が生じてしまうため、導入に際しての要件や手続きは一定の厳しさをもったものとなっています。事故や健康被害が発生して訴訟になるリスクもありますから、安易な導入・運用はビジネスにとってもおおいなマイナスです。
対象となる労働者も、雇用する使用者も、理解不足のまま進めることがないよう十分に注意し、能力を最大限に発揮するための仕組みとして機能するよう、検討しましょう。
(画像は写真素材 足成より)
おすすめの記事

掃除や家事は運動になる!家事の運動量や消費カロリーはどのくらい?
2024.05.15 - コラム

食いしばりや歯ぎしりは歯を痛める原因に!改善の方法は?
2024.05.10 - コラム

やむを得ない事情で夜遅くの食事に 遅い時間に食べてもいい食品は?
2024.05.03 - コラム